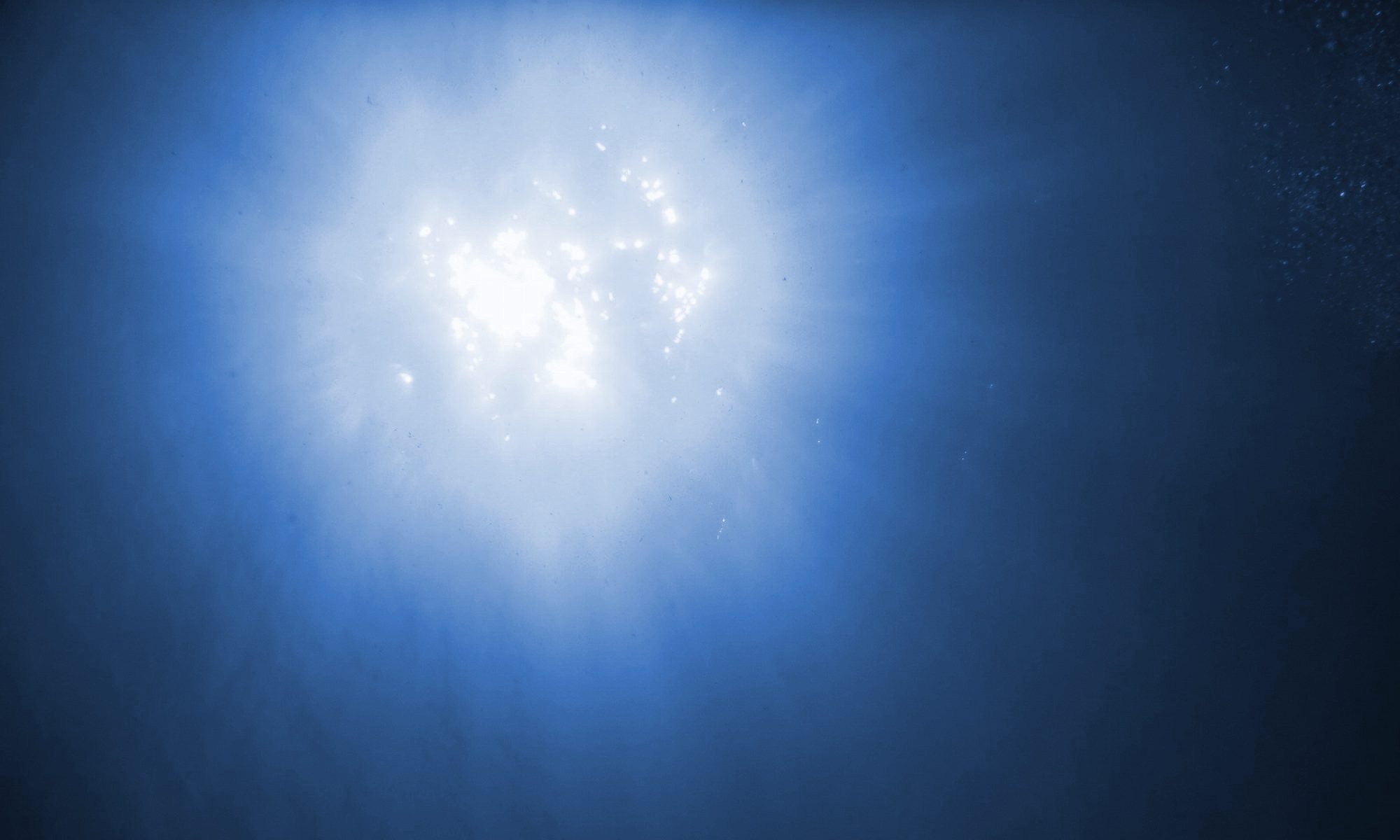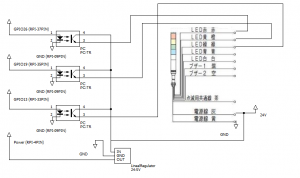夏の在宅期間中にフリーになった通勤時間の合間を縫って、車学に通って大型二種免許を取ったんだけど、その気づいたことレポート。教習中の写真は撮らないようにと教官に言われたorz
(技能)
日野ブルーリボン(フィンガーシフトMT)で教習した、基本的にMT普通自動車と操作は変わらないんだけど以下注意点
・急加速しない:バスは急な加速ができない乗り物なので黄信号での交差点進入はできないと考える。黄信号で交差点付近に接近しないよう予め、遠くから速度調整を行っておく。
・ギアチェンジに時間がかかる:フライホイールが巨大なため、クラッチをゆっくり繋がないとエンジンが止まる(てかローライダーみたいにガクンガクンってw)。半クラを(バイクのように)極端に意識しなくても発進はできるが、普通車よりも遥かにゆっくりクラッチを繋ぐことを意識すること。坂道発進もゆーっくり半クラするイメージ。
・右左折時、後輪は遥か内側を通る:折れる方向と逆側のミラーを(場合によっては対向車線を使うことも考慮)道の端まで持っていくイメージで曲がらないと、歩道に乗り上げたり側面を曲がり角にぶつける。S字も折れる方向と逆のポールにミラーを持っていって、沿わして曲がって行くイメージ。ちな隘路のハンドルを切り始めるタイミングは、入りたい道の中心の延長線上の真上に運転席が来たとき。
・坂道は恐ろしい:下り坂だとすぐ加速がついて恐ろしい。特に重量が半端ないから速度がつかない時点でリターダとか予め作動させとく。上り坂も恐ろしい、今のバスは馬力がないので、3速で登ろうものなら失速してしまう。かと言って2速だとエンジンがやかましいと感じるが、登ってる途中で3速→2速シフトは恐ろしい。
・鋭角:コツは鋭角部分でのハンドルを切るタイミング。運転席が鋭角の先にある車道の外に来たときめいいっぱい切ってやる。
・転回:後輪の位置よりも若干手前が角にかかる感じでハンドルを切っていくとうまくいく。ミラーの凸度が大きいので、まっすぐ入ったら、左右の車と道路境界の形状が台形になる。
とこんな感じ。
(学科)
学科対策は車学のテキストと以下の問題集一冊(改定前の方)で一発合格できた。